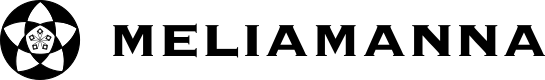はじめに
現在僕が管理している自然栽培スタイルの菜園では、主に雑草対策を目的として黒のビニールマルチを使用しています。ほとんど全ての畝においてです。
これを使っている理由としては、最初に菜園の基礎を教えてもらった仲間が使っていたからとか、ネットで検索すると主にそれが使われいるからとか、自分でも実際に使ってみて雑草管理に効果があると感じているからとか。ちょっと受動的にモノを選んじゃってるきらいが無きにしも非ずですが、まあ、ビニールマルチは普通に良いです。
しかし、最近仲間の方々と議論したり、本と睨めっこして学びを深めていくうちに
1. 黒のビニールマルチは、特に夏の時期に地温が上がりすぎる。反面、草マルチは地温の上昇を抑えてくれる。
2. 草マルチを使用すると、菜園環境の生物多様性が上昇する。
ことを学びました。
そして考えを巡らせた結果「自分が目指す菜園にとっては、草マルチの方が良くないか?」との考えに辿り着いたので、2024年の冬作以降は、ほぼ全面的に草マルチに切り替えてみることにしました。
草マルチを試した結果についてはいずれ報告することにして、今回の記事では、地温そして生物多様性の観点から、僕がビニールマルチから草マルチに切り替えてみようと思ったきっかけについて深く掘り下げてみたいと思います。
なおマルチングと聞いた時、そのイメージや、メリットデメリットが頭に浮かんでこない場合は、まず『マルチング(Wikipedia)』をご覧になられることをオススメします〜。
では本題に移ります!

草マルチに切り替えてみることにした!
地温から観たマルチング
黒のビニールマルチは夏に地温が上がりすぎる?
僕がビニールマルチから草マルチへ切り替えようと思った理由の1つ目。
それは黒のビニールマルチは夏に地温が上がりすぎるからです。
いきなり寄り道しますが、まずは前提の話として、黒のビニールマルチが菜園にもたらしてくれる効果は
・黒色で太陽の光を遮断し、土中の雑草種子を発芽させない。
・黒色の保温効果によって地温を上げ、作物の発芽や生育を良くする。
の2つがメインであると認識しています。
畝の一面をビシッと覆って雑草を抑制させることができるので草刈りの手間がだいぶ省けるし、特に冬から春先にかけての冷える時期には地温を上げて作物の発芽や生育を助けてくれるしで、すごく優秀な資材です。
だけど、ここで問題が発生。確かに黒のビニールマルチは気温の低い時期に地温を上げてくれるメリットもありますが、ここ最近の夏の酷暑ではこれがデメリットに転化すると思われます。
これはぶっ倒れそうなくらい暑い夏のこと。仲間の方と、地温とビニールマルチについて議論していた時のお話です。
 うちの畑ではさー、もうビニールマルチ剥がしてみたんよね。
うちの畑ではさー、もうビニールマルチ剥がしてみたんよね。
 マジですか!? やっぱりこの暑さでビニールマルチだと地温が上がりすぎますよねー。
マジですか!? やっぱりこの暑さでビニールマルチだと地温が上がりすぎますよねー。
 そうそう。今の気温が37℃で、それに何℃かプラスされるはずやけん、地温40℃超え!?
そうそう。今の気温が37℃で、それに何℃かプラスされるはずやけん、地温40℃超え!?
 それはヤバいかも! うちの畑でもマルチ剥がしとこう!
それはヤバいかも! うちの畑でもマルチ剥がしとこう!
実際に地温計で計測したわけではないですが、近年の夏にビニールマルチを使用していると「もう熱い風呂に浸かっとるやん」状態になっているのではないかと推測されます。
こんな状態でも作物の生育が滞らなければ問題ないのですが、僕が2024年の夏にビニールマルチを使って栽培していたオクラやキュウリなどは、特に暑さが酷かった8月や9月には生育がほとんど停滞している様子で、ちょっと気温が落ち着いた10月頃に巻き返して成長している様子でした(雨が全く降らなかったのも影響してると思うけど)。
オクラなんかは生育に高い気温や強い光を必要とし、熱帯や亜熱帯の地域で広く栽培されている作物ではありますが、そんなオクラでも生育適温は20~30℃ほど(BSI生物科学研究所 2023)。酷暑による作物へのダメージを軽減してあげて、できるだけ長い期間収穫を楽しむためには、黒のビニールマルチを用いた栽培は避けた方がいいのではと考えました。

草マルチは地温を下げてくれる
そんな黒のビニールマルチの代わりとして使えそうなのが、草マルチです。
草マルチとは、主に菜園の通路などに生えている雑草を刈り取り、それを畝の上にどっさりと敷くマルチングの方法です。葉が長くて細いイネ科の雑草を使うと良いなどの意見もありますが、ドクダミやセイタカアワダチソウなど地下茎で増えるタイプの雑草を除き、僕はどんな種類の植物でも使っています。
この草マルチですが、一般的に使用されるビニールマルチと同様、地表を覆うことで太陽の光を遮って雑草の発芽を抑制する効果があるのに加え、地温の上昇を抑える効果が期待できるとのこと。
以下の動画は、僕や畑仲間がこぞって参考にしている、イギリスで20年にもわたって自然栽培を実践されていた今橋さんの動画ですが、この動画内でも
「草マルチは土中の湿り気を保つことで地温を下げることができる」
「暑い日本の夏にも、草マルチで地温を適温までもっていけるんじゃないか」
という趣旨のことを仰られています。
生物多様性から観たマルチング
僕がビニールマルチから草マルチへ切り替えようと思った理由の2つ目。
それは草マルチをすると菜園の生物多様性が上昇するからです。
具体的に言うと、作物にとっての害虫を捕食してくれる天敵が菜園に定着してくれる可能性が高まるからです。
以下、最近僕がとても参考にしている、杉山修一さん著『ここまでわかった自然栽培』から引用します。
野菜栽培で使われる黒ポリマルチは地表面の温度が上昇するので、徘徊性のクモなどの天敵にとって環境を悪化させる。黒ポリマルチの代わりにワラマルチを使うことで、コモリグモやカブリダニなどの天敵が増え、害虫被害が減ることも報告されている。
『ここまでわかった自然栽培』
まず、ここでも黒のビニールマルチによる地温上昇が問題視されていますね。地温の上昇は、作物の生育適温を優に通り越して株にダメージを与えてしまう可能性があるだけに留まらず、害虫の天敵となる昆虫やクモ類にとっての環境悪化も招いてしまうと。
ちなみにコモリグモはヨトウガなど、カブリダニはハダニ類の天敵となることが知られています*2。農薬(殺虫剤)を使用しない栽培スタイルにおいてはたいへん有用な土着の天敵であり、ビニールマルチからワラマルチ・草マルチに切り替えるなどして、これらが菜園に定着できる環境を整えてあげることはマストなんじゃないかと思います。
またマルチングの話からは逸れてしまいますが、『ここまでわかった自然栽培』では以下のような耕起や草刈りに関する話も登場します。
・耕起により引き起こされる土壌かく乱は、捕食性の徘徊性クモなどの節足動物の棲息場所や繁殖地を破壊し、安定した棲息地を求め天敵は移動することになる。そのため、毎年耕起される野菜畑は、耕起されない畑より徘徊性クモ類などの天敵の種類や密度が低下することが知られている。
・うね間に生える雑草を根から排除するのでなく、地上部を草刈り機で刈り、雑草の過繁茂を抑制しうね間の植物多様性を高めることで、ヨトウガなどの捕食天敵であるコモリグモ、ハネカクシ、ゴミムシが増えた研究例もある。
・ヨーロッパの大規模ムギ畑では、耕地の中に耕起をしないうねを作り、そこに多年生イネ科牧草を植えて徘徊性のクモやカブリダニの棲息場所や越冬場所を人為的に作る、ビートルバンクが害虫防除技術として普及している。
『ここまでわかった自然栽培』
このように、毎度々々耕起する、雑草を取り除きすぎる、などといった過度なかく乱を控えることも、土着の天敵にとっての生息場所さらには越冬場所を提供し、天敵が一年を通して菜園に棲みついてくれる環境を作る上で重要なことが分かります。
上の引用でも言われていますが、植物と違って脚や翼を持つ昆虫や動物は、環境が優れないと分かった途端により良い場所を求めて一瞬で外へ出ていってしまいますからね。もし菜園において「農薬は使わずに、土着の天敵を含む生物多様性を高めることで害虫被害を抑えたい」と考えた場合、人間ができることは、自然をよく観察して理解し、ありとあらゆる生物が棲みつく環境を作ってあげること。これくらいだと思います。
そしてもちろん自分が目指すのはこのような菜園の在り方なので、今回引用している文章を読み、一年を通して全面的に草マルチへ切り替えてみようと即決したわけです。生態系が相手なので、道のりは長く時間がかかるだろうけど、やっぱり目標とする場所にブレはありません。

けどやっぱり、ビニールマルチを使いたいこともある
こうして全面的な草マルチへの切り替え宣言をしたところで、最後にワガママなんですが…。
やっぱりビニールマルチを使いたい場面も出てくるんじゃない!? と考えています。
例えば、ニラ。

これは現状、ニラを黒のビニールマルチを張りながら育てている光景ですが、これが草マルチになる光景を想像しても自分はなんだかしっくりこなかったんですよね。その理由を言語化してみると「株の周りを綺麗に除草するのが難しそうで、すぐ草に埋もれてしまいそうだなー」とか「収穫する時、マルチの草とニラの葉が一緒に混じっちゃいそうで面倒くさそうだなー」とか。
ま、実際やってみないと分かんないんですけど。
なので、まずは例えばオクラ・トマト・大根・ツル性のマメ類など、株元がドンと1本立ちしている作物を中心に草マルチに移行し、ニラをはじめとする葉物野菜では実験的に草マルチを試していこうかなーと考えています。
さいごに
今回の記事ではビニールマルチはやめにして、草マルチに移行していこうと思った話について、地温それから生物多様性の観点から深く掘り下げてみました。
しかし今回の内容の中でも特に、草マルチによって天敵が棲みつきやすい環境を作ることに関しては、引用した『ここまでわかった自然栽培』でも指摘されていましたが、全くもって容易な仕事ではなく、また未開拓分野のため体系的な防除技術が確立されているわけではありません。たぶんめちゃくちゃ長ーーーい道のり。
けど僕個人的には、土着の天敵をもってして害虫を抑えようとの試みはすごく魅力的な世界線だと思うし、菜園を自然環境の一部であると捉えると至極当たり前な世界線だとも思います。これを目指し実行する人が増えて知見が積もることで、少しずつ大まかにでもいいから体系化が進めばいいなーとも。
あと、せっかく自分達の生活のすぐそばにある菜園なんだから、昆虫も、カエルみたいな両生類も、鳥たちも、哺乳類も、皆わんさか暮らしてた方が賑やかじゃないですか。そしてこんな〈わんさか状態〉から〈平衡状態〉が生まれた時、作物を齧ったり病気にしたりする生き物もいて、けれどそいつらを捕食・寄生する生き物もいて…というまさに野生の調和がとれた場が完成するんだと思う。
最後の最後でちょっと抽象的というか、理想論に走ってしまいましたが、あとは実験と改善を繰り返すだけですねー。この過程がいちばん楽しいよね!
参考にした文献
BSI生物科学研究所, 2023. 「実用作物栽培学」オクラ. (2024/12/26時点)
https://bsikagaku.jp/cultivation/okra.pdf
杉山修一, 2022. ここまでわかった自然栽培 農薬と肥料を使わなくても育つしくみ. 農山漁村文化協会, 埼玉, 179pp.
関連記事
MELIAMANNA(メリアマナ)では、自然栽培への取り組みを通して”食”としての植物の可能性を深く探り、発信しています。
〈自然栽培〉のタグがついた記事はこちらから。