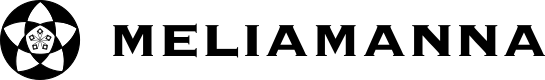はじめに
2023年の1月に久高島を初めて訪れてきたので、今回の記事はその旅行記。日帰りだったけど、久しぶりの一人旅でした。
タイトルでも仄めかしていますが、この島ではとにかく鬱蒼と茂る植物たちに圧倒されていました。
そんな植物たちの姿を早速紹介したいところですが、僕が久高島に行くきっかけとなった、小さいけれどとっても大切な出来事があるので、まずはそれについて書いてみますね。また沖縄の地理に馴染みのない方もいると思いますので、久高島の簡単な紹介もしてみます。

久高島についてと、訪れるきっかけになった出来事
まずは、久高島について簡単に紹介してみます。
久高島とは、沖縄本島南部の南城市という町からフェリーで東へ25分ほど進んだ所にあるとても小さな島です。もしもノンストップで歩けば、1周するのに1時間半しか要らないくらいの。島の形は南北に伸びる縦長で、その南部に小さな集落があるだけで、残りは森と海と畑。島の至る所には、御嶽(うたき)や拝み所(うがんしょ)などの聖地が存在しています。
フェリーで久高島の港に到着すると、皆ちゃりんこや電動スクーターを借りてから島の中を思い思いに巡っています。中には、自前の自転車をフェリーで持ってきてる人も。もちろん俺みたいに徒歩で巡ってもよし。歩きで巡ると、心地よい海風と手付かずの自然を肌に感じながら島の隅々まで思う存分堪能できます。ゆっくり歩かないと視界に入ってこないものって沢山あるしね。
それと、自分はまだまだ勉強不足なのでここでは多くを語れませんが、琉球神話では久高島最北端のハビャーンに創世神アマミキヨが降臨したとされていることや、古来から続く神事の一部が現在でも執り行われていることなどから、久高島は民俗学的にたいへん重要な島とされており、「神の島」とも呼ばれています。実際に島の中を歩いていると、点在する聖地で祈祷を行なう方々の姿も見られました。
そんな久高島に僕が行ってみようと思ったきっかけはというと…..
立て続けにヒトに勧められたから。以上。
ごくフツーの理由ですよね。だけどよくよく考えてみると、ある1つの場所を何人もの方から立て続けに勧められることなんてそうそう無くて、これは人生が「今のタイミングで久高島に行っとけ」って言ってきとるわと解釈。パウロ・コエーリョの『アルケミスト』で言うところの”前兆”というやつでしょうか。すぐさま予定表・天気予報とにらめっこしつつ、2023年1月のある快晴の日、体に無理言って早起きしてもらって久高島に向かいました。
この2023年とは、僕が沖縄で過ごした6年間の最後の年。しかも2023年の3月にはもう福岡に帰ることに決めていたから、久高島に行くことになったのはほんとうにギリギリのタイミング。それまでは「釣り好きの友達がよく行ってんなー」ぐらいのイメージしかなかった島に、こうして自分が導かれていくなんて人生なんとも不思議なものです。
そして久高島に向かうとなった時、とても楽しみだったのがその大自然。
久高島を勧めてくれた人は、親戚だったり、友達だったり、行きつけの植物屋でたまたま出会った人だったりですが、みんな口を揃えて
「久高島は植物のパワーがえげつないんだよ!!」
「何だか久高島の植物は勢いがすごくて生い茂ってるんだよ!!」
「いや、実際行ってみたら絶対わかるから!!」
と言ってくるのでした。
もう、こんなこと言われたら自分の目で確かめに行く他ありません。
ということで、久高島へいざ上陸!

久高島で出会った植物たち。このオーラは現実? それとも幻?
時刻は朝の8時半ぐらい。
フェリーが着港し、久高島の地に降り立った瞬間、というか船が港へ向かってアプローチしている瞬間から、海岸線の岩場に生い茂っている植物のオーラが普通とは違うことに気が付く。何だか言葉では説明できないけれど、何だか違う。緑の深さ? それとも樹勢? いや、他に気づけていない何かがあるんだろうか?
一旦、この感覚はバイアスだ、ということにしてスルーしてみる…..。
で、まずは集落。
そこ一帯は、のほほ〜〜〜〜〜んとした空気感で満ち満ちていて、どこか適当な琉球古民家に転がり込ませてもらって、まだまだ朝なのに昼寝でもしたくなるような気分。日常生活では次へ次へを目指してひた走る脳みそだけど、この集落を歩いていると結跏趺坐で今現在にギュインと戻ってこれるような、そんな感じ。そしてある民家のお庭には、俺の大好きなカニステルというフルーツが生っていて、塀の外側から手を伸ばしたいイリーガルな欲求を必死に抑えつつ、集落を抜ける。
集落から外れて北に向かって進んでいくと、道の数は極端に少なくなっていく。島の真ん中を、最北端のハビャーンまで続く1本道がスコーーンと走り抜けていて、その脇に細い未舗装の道が数本走っているくらい。
今回は特に地図もちゃんと見ないまま、直感に従って適当に歩いてみる。最初はどうやら海岸に沿った道を歩いていて(といっても海岸に沿った道がほとんどなんだけど)、定期的に現れる聖地のガイド版を読み込み、そして見学させてもらいながら、北へ北へと向かって歩みを進める。
モンパノキ
ここでやっと植物の話になるんですが、初めに紹介するのはモンパノキ。〈紋羽の木〉とも書きます。紋羽とはいわゆるビロードのことで、モンパノキの葉っぱを触ってみると、その名の通りフッカフッカしていてめっちゃ気持ちいい。
熱帯地域が出身の植物で、海岸の砂浜や岩の上という環境を好むので、沖縄の海岸では大概どこでも発見できます。観賞用で売られているのはまだ見たことがないですが、沖縄ではしばしば盆栽にされることもあるようです。
さて、久高島の海岸で見かけたモンパノキはというと…..。普段沖縄本島で見かけるものよりも、やっぱり威勢がすごくいいように感じる。葉っぱがシャキッとしていて、照りが綺麗で、樹勢が良いように感じる。
これは現実? それとも、バイアスが創り出してしまった幻なのでしょうか??
何だか威勢がいいような気がするモンパノキ
そんなモンパノキを横目に、島の最北端へと向かい、またスタスタと歩いていく。先程と同じように、途中途中に出現する聖地に立ち寄りつつ進んでいくと、やがて道は融合してハビャーンへと続く1本道だけになってしまった。
ビロウ
この1本道沿いは〈ビロウの杜〉と呼ばれていて、その名の通り道の左右に広がる杜にはビロウというヤシの仲間の植物が群生している。そしてまたここでも、植物はは目を見張るような勢いで生きていた。
ビロウは漢字では〈蒲葵〉と書き、方言ではクバと呼ばれています。日本国内では南西諸島や、九州・四国の南部に分布する植物で、シュロに似た植物と言えばシルエットは想像しやすいでしょうか。
葉には薬効があり、民間で解熱剤として利用されることもあります。*1
1本道の脇にあったガイド板を見てみると、久高島の祭祀行事ではビロウを扇や神座として利用すると書かれていて、やっぱりこんな風に自然と人間が関わり合うのが本来の姿なのかな、などと考えつつ、まだまだゴールの見えない1本道を歩いていく。
くそ、暑くなってきた。1月だけど、晴れてしまえば日差しはきつい。そういえばさっき、砂浜で焼いてるおっさん居たな。横を電動スクーターで抜かしていく観光客が、ちょっと憎たらしい。

ビロウの林の影で昼寝をするクロネコから見送られつつ、1本道を進み続けると、やっとのことで目的地だった久高島最北端のハビャーンに到着。不思議な名前のハビャーンでだけど、ここはカベール岬とも呼ばれるらしい。岬と呼ばれるぐらいなので、ここには綺麗なビーチがあるというわけではなく、ゴツゴツゴツゴツした石灰岩が海岸の植物にびっしりと覆われている場所。
岬の上に仁王立ちしながら眺める海は言葉にできないぐらいの魅力を持っていて、香りの引き立った潮風を思いっきり吸い込みながら、岬の崖と浦波が作り出した虹を眺めていると「他にはもう何も要らない」という感情になってくる。
俺の尊敬する細美武士というバンドマンが『What I Left Today』という曲の中で
“If this was the last day of my life, I’d be lying on the beach.”
(もし今日が人生最後の日なら、俺はビーチにでも寝っ転がってるだろうね)
と歌っているんだけど、そんな感情とシンクロしちゃうような感覚だった。
このハビャーンという場所は俺にとって、それほどの魅力を持ったとてもお気に入りの場所になった。人の少ない方へと歩いて行って、裸足になって昼寝していると本当に気持ちがよかった。人生のどこかで絶対にまた来るだろうな、という強烈な直感に見舞われる。
ウコンイソマツ
ここで、久高島で出会った次なる植物の紹介をしてみます。その名はというと、ウコンイソマツ。漢字では〈鬱金磯松〉と書きます。この植物は琉球列島と台湾の一部に分布する植物で、先ほどのモンパノキと同様、海岸の岩場という環境を好みます。
茎や葉には薬効があり、民間で解熱薬や抗炎症薬として利用されることもあります。*1
そして何と言っても!! この植物のカワイイポイントは、その樹形にあるのです。ハビャーンのゴツゴツとした岩場の上を歩くと、そこには無数のウコンイソマツがいて、珊瑚のように綺麗に枝を伸ばしているものもあれば、何故そうなったのかわからないけど輪っか状の樹形をしているものもあり。そんな個性溢れる姿が、石灰岩の岩場から顔を覗かせているのが、ほんとうに可愛らしい。とにかく、写真を見てみてください!
久高島の岩場に生える個性溢れるウコンイソマツたち
ね!? 幹の形がとっても可愛らしくないですか!? 盆栽として楽しまれてきた歴史があるのも納得。なかなか見かける機会はないですが、もしご縁があればぜひ手に入れてみてください〜。俺も欲しいな!(絶滅危惧種に指定されてますので、もしご購入の際は野生採取ではなく、栽培のものを!)
モクビャッコウ
続いて紹介する植物はモクビャッコウ。漢字では〈木白香〉と書きます。方言ではイシギクとも呼ばれています。琉球列島に分布している植物で、モンパノキやウコンイソマツと同じく、海岸の岩場を好みます。
このモクビャッコウ、花こそ地味ですが、本当に綺麗なシルバーリーフをしていて個人的にだーーい好きな植物です。沖縄に住んでいた頃は自分でも鉢植えのモクビャッコウを育てていた経験があって、南側のベランダに置いて強烈な日光に晒し、そのギラギラとしたシルバーリーフを楽しんでいました。
そんな、自分の家に置くほど大好きなモクビャッコウ。大好きな気持ち故、家で育てていたものも、散歩の途中で見かけたものも、普段からシルバーの綺麗な葉っぱを触りまくっていたので、モクビャッコウのことはよく知ったつもりでいました。
だがしかし!!
久高島で見つけたモクビャッコウの葉っぱにいつものごとくそっと触れてみた瞬間、衝撃が!!
普通よりも2倍ぐらい葉っぱが厚かったんです。
ん?? どういうこと?? これは??
確かにどの植物でも、陽がよく当たる場所だと葉が厚くなったりすることはあるけど、それにしても、この久高島のやつは厚すぎる気がする。中には「あれ? もうこれは多肉植物なんじゃないか?」と思っちゃう程の厚さを持った葉っぱも。
これも、久高島という環境が作り出した不思議な現象なのでしょうか??
3枚目の写真はおまけで、近所の散歩道でお気に入りだったモクビャッコウ。かっこいい。
さいごに
生活の拠点を沖縄から福岡へと移すギリギリのタイミングで、導かれるようにして訪れた久高島。
そこでは、久高島を勧めてくれた人が放った「植物のパワーがえげつないんだよ!!」という言葉の意味を目の当たりにし、その感覚を感じ取りつつも、いったい何がそう感じさせるのか具体的には分からないまま島を後にすることに。
いつになるか分からないけど、もしもまた久高島を訪れるタイミングが巡ってきたら、次こそは「植物のパワーがえげつないんだよ!」という言葉の本当の意味を掴めるように、精神的に成長しておこうと思いましたとさ。
ではまた!!
参考文献
*1 『改訂・沖縄の薬草』著:吉川敏男
関連情報
【公式ホームページ】久高島フェリー
久高島行き定期船の料金や時刻表、港へのアクセスなどについて書いてあります。
https://kudakakaiun.jimdofree.com
日本とユダヤのハーモニー&古代史の研究
『琉球諸島を一大拠点としたイスラエルの民』というタイトルの記事です。
久高島をはじめとした琉球諸島の文化や信仰の成り立ちについて興味のある方は、こちらのサイトを追ってみて下さい。
https://www.historyjp.com/article/390/#i-5
日本人の魂の原郷 沖縄久高島
神社めぐりをしていたらエルサレムに立っていた
関連記事
旅行記の一覧はこちらから。