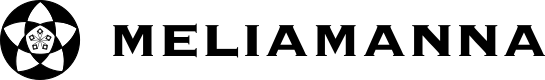はじめに
福岡県糟屋郡久山町のフリースクール / オルタナティブスクール〈ほしのこども学舎〉さんと提携して、子どもたちに向けた体験学習を開催しています。
2025年5月のテーマは、採集したヨモギで草餅を作ってみよう。
ここ福岡では、もう半袖1枚でも大丈夫そうなほど暖かい季節。それに伴ってヨモギも勢いよく成長している様子。春先、葉のサイズはまだ小さく、まだ寒い夜に抵抗するように表面まで白い繊毛に覆われていたけれど、5月に入ると葉のサイズは大きくなり、表面の繊毛はほぼ消えて青々とした色味に。葉を揉んだ時の香りもグンと濃くなります。
そう、今からがヨモギの風味を最大限に楽しめるようになる季節なんです! しかも繊毛が少なくなるから食感がモシャモシャしない!

繊毛が多く、食べるとモシャモシャしがち。
ヨモギを採集して草餅作り
ヨモギの採集
ということで外に飛び出して、ヨモギの葉をみんなで採集。
今回はヨモギの種類までは教えなかったけど、採集したのはカズザキヨモギ Artemisia indica var. maximowiczii です。そこら辺を歩けばすぐに見つかるヨモギは大概この種で、今の時代の草餅に使われている代表的な種。他にも、下腹部の冷えや生理痛に対する薬草として用いたり、お茶として単純に楽しんだり、葉の裏面の繊毛は艾(もぐさ)と言ってお灸の原料として使うことができたり。
実際に採集する時、何も教えてないのに「ヨモギとトリカブトを間違えないようにしないとね!」って自分から言ってくれた子もいて、自然を生き抜く視点が身についていてとっても感心しました。植物の存在がしっかり視界に入っているね。
じゃあ次は具体的に、トリカブト類と間違えずにヨモギを採集するためには
・まず葉の形をしっかり覚えること
・ヨモギは葉の裏に白い繊毛がびっしり生えていること
・葉をちぎったり揉んだ時に THE ヨモギの香りがするか確かめること
などを意識することを一緒に学んでいきました。
今回の採集場所はトリカブト類が生育するような環境ではなかったけれど、こういった心がけを忘れずに採集することはとっても大切なことですね。子どもたちほど、形のほんの小さな違いにも敏感だったりするので、その点いつも勉強させてもらってる。

…..と、ヨモギを頑張って採集したみたいに書いたんですが、実際に子どもたちが釘付けになっていたのは、ヨモギと同じ場所に生育していたクサイチゴの真っ赤な実の方で…。刺々しい茂みの中に躊躇なく突っ込んで行ってはクサイチゴの実を口に放り込んでいたのでした(もちろん大人も一緒に釘付け)。
ま、青々としたヨモギの葉っぱより、鮮やかな赤に色づいたクサイチゴの方が魅力的で食べたいと感じるその感覚が自然だよね!

草餅作り
お次は室内に戻ってきて、草餅作り。
今回は手軽に、白玉粉を使った草餅のレシピを紹介しました。作り方の手順を板書したら、あとは自由に協力しながら皆でお料理。ヨモギの葉を潰す際には、ミキサーを使ってみたり、昔ながらのスタイルですり鉢を使ってみたりと、いろいろな方法を体験してみました。

色々と紆余曲折ありながらだったけど、無事完成!
「低学年の子は草餅を美味しいと感じてくれるかなー?」ってちょっと心配してたけれどそれは杞憂で、「黒蜜と蜂蜜はどっちが合うかな!?」とか言いながらめちゃくちゃ美味しそうに食べていました。よかった!

子どもの天才的な発想でノイチゴ餅も作ってみた
ヨモギ餅に加えて、子どもの「ノイチゴでもお餅作ってみたい!」との天才的な一声で、採集したクサイチゴの果実を使ってお餅を作ってみることに。
このアイデアを聞いた時、まさに青天の霹靂な衝撃を受けてしまった。この日はヨモギ餅だけ作る気で来ていたし、果実を使ってお餅を作るなんて発想を持っていなかったから。こういった出来事が次々に起こるから、やっぱ現場が一番おもしろいな!って思う。
それに〈ほしのこども学舎〉さんが、子どもたちが思い浮かんだ自由なアイデアを何の躊躇もなくアウトプットできる場であることを、一緒に活動させていただいている身として、とても誇りに思っている。毎回もちろん学習内容をきっちり計画してから行くんだけど、皆のアイデアで、雪だるま式に体験学習の魅力度が増していると感じている。
で、完成したクサイチゴのお餅の写真を載せて記事を締めますね。
薄ピンクのとっても可愛い見た目で、甘酸っぱい香りがほんのりと優しく漂ってきて、種子のプチプチとした食感がとっても楽しくて。すごく思い出深い体験授業になりました!