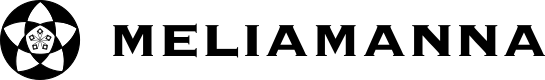例年に比べて、今年は小説に積極的に手が伸びない年だった。
理由は色々思いつくけど、ここではなんとなく濁してみる。
で、そんな年の師走にもなって、今年最高の小説に出くわしてしまった。
お風呂に入って温かくなっていたはずの指先が、夜更けの冷気にさらされて芯から凍えていくことや、翌朝、目の下にできてしまう大きなクマが全くもって気にならないほどの、最高で壮絶な読書体験だった。
それは『香水 ある人殺しの物語』という小説で、PARCOでやってたBook Park Clubというイベントで見つけて、迷いなく購入したものだった。
物語の内容をここで語るのはつまらないから省くけれど、それは生まれながらに天才的な嗅覚を持つ”変態調香師”が主人公の小説で、少し変色して甘い香りを放っている古いページに打ち込まれた文章には、この世に存在しているありとあらゆる匂いが所狭しとひしめきあっていた。
想像しながら読むと、鼻腔がぶっこわれて顔が歪んでしまいそうになるほどの醜い匂いから、身骨が全てとろけてなくなってしまいそうになるほどの魅惑的な匂いまで。
鼻は効く方だけど嗅覚的に天才ではない俺にとっては、この小説に描かれているような、フランスの全てが集結するパリの街に鎮座している匂いの束を主人公が1本1本紐解いていく様子や、初対面の人間の体臭を一息感じるだけでその人との付き合い方がストンと一発で理解できてしまうような特性、これまで経験した香りを脳みその中で自由自在に調香できる才能には、到底理解が及ばないけれど、(純粋無垢な殺人を含めた)生き方の全てを匂いが支配してしまうような世界に深く没入させてくれたこの小説は、読了するとすぐに、そっと一軍の本棚へと加えておいた。
そして俺はやっぱり、視覚だけではなくて、嗅覚みたいなその他の感覚もふんだんに使われた描写がとても好きだと思った。
こんな理由からも、川上未映子さんの文章がとても好き。
さて、あと2週間もすれば冬至がやってくる。
1年が収束し、そして復活へと向かう、とても大切な日。
今年のフィナーレを祝うように、燻んだ冬の色彩に山茶花が紅を差している。
センリョウは、実を鮮やかに色づけて祝杯をあげている。
俺は、この前熊本で買ってきた日本酒でも開けようか。