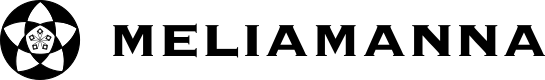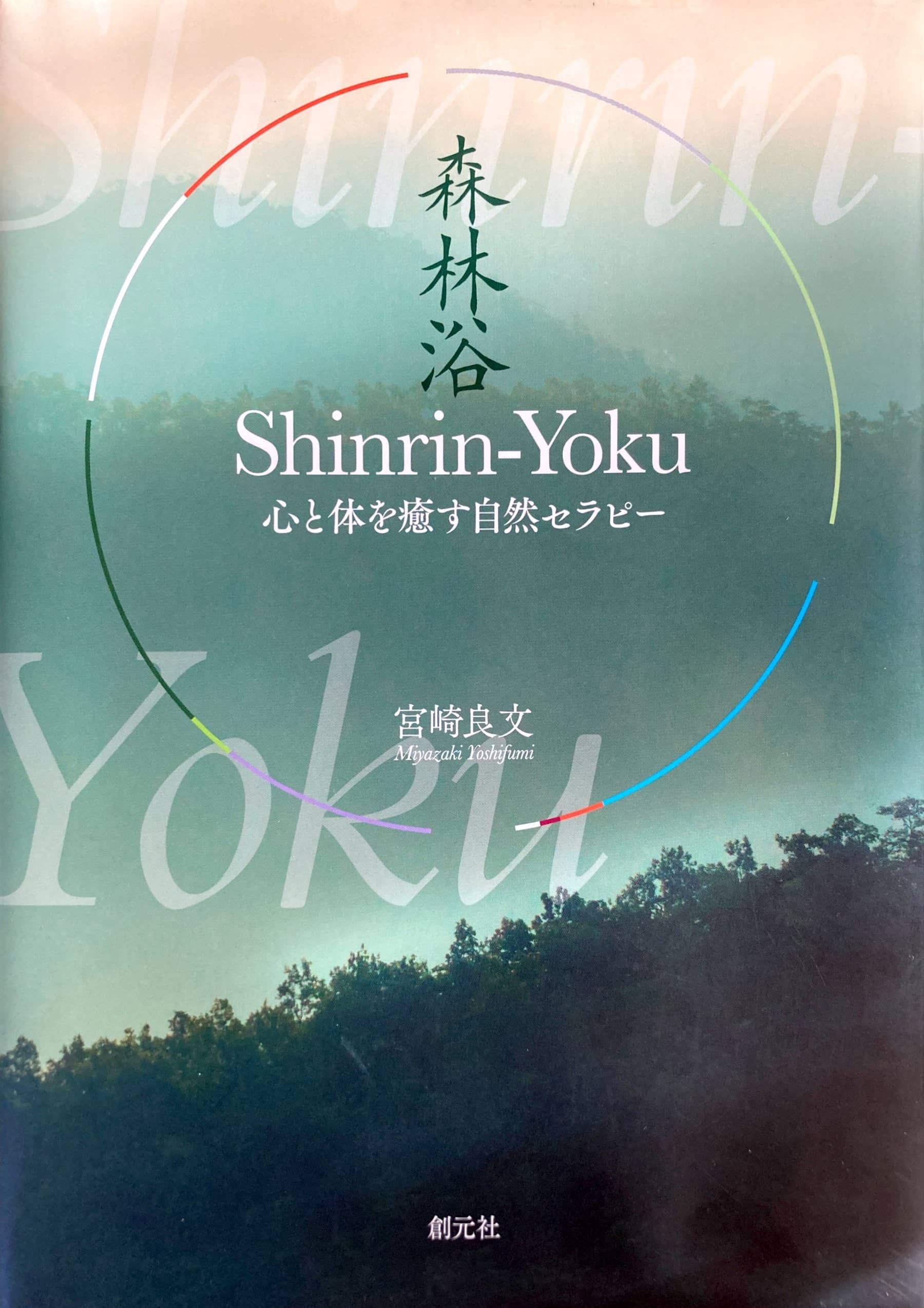[toc]
はじめに
サイトを見に来てくれたみなさん、こんにちは!
MELIAMANNA(メリアマナ)代表の有吉です。
MELIAMANNAとは、大学院で植物を学んだ代表が”衣食住”に植物を取り入れた暮らしを楽しみ、探求することをテーマとして活動しているサイトです。
今回の記事は『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』の読書日記。
最近とあるきっかけでこの本を手に取ったのですが、その内容がとても興味深く、生活の豊かさがどこまでも上昇しちゃいそうな内容だったので、本の内容や、読んでみた感想について紹介してみたいと思います。
この本のテーマは僕が読んでみて思うに、森林浴で自然の中に身を投じることや、植物と接することが(眺める・嗅ぐ・触るなど)、ヒトの心や身体に対してどのような影響を与えるかを科学的に解き明かすこと。
「森の中で過ごすと、なんとなく心が落ち着いてくるなあ」
「しかも、思考がクリアになってインスピレーションが湧いてくるなあ」
「植物のかわいい形や花の匂いには、いつも癒されるなあ」
などといった、誰しもが感じたことがあるであろうなんとなくの感覚が
「なるほどそういう仕組みか!」という確かな感覚に変わっちゃうような本です。
今回の記事は
・なぜ『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』を手に取った?
・そもそも森林浴って何だろう?
・この本のここが面白い!読んでみた感想などについて。
・気軽に始められる森林浴以外の自然セラピー
の4段構成で進めています。では早速!
Shinrin-Yoku(森林浴): 心と体を癒す自然セラピー
森林浴はなぜ、心と体を健康にするのか?
私たちは自然環境に適応した体で生きてきた。そのため、現在の人工化された都市社会において、ストレスによる心身の不調が社会的な問題になっている。
本書は、海外でも注目を集める著者の英語による著作を逆輸入。自然由来で低コストであり、ストレス軽減、リラックス効果、予防医学的効果のある森林浴について、科学的研究データに基づいて解説。
森林浴を体験できる場所や具体的なプログラムをはじめ、自宅で手軽に取り入れることができる、フラワーアレンジメントや観葉植物、木材、香りなどの効果も紹介。自然と触れ合うことで、心と体を健康に。
なぜ『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』を手に取った?
僕が今回この本を手に取ったのには、はっきりとしたきっかけがあります。
それは、前回の読書日記シリーズで紹介した『植物は〈知性〉を持っている』に書いてあった、植物が近くにあるだけでヒトは本能的にリラックスするという事実に衝撃を受けたから。
さらにこの本では、身近に緑豊かな環境がある場所では、そうでない場所よりも
・入院患者に必要な鎮痛剤の量が少なくて済み、入院期間が短かかった
・学生のテストの成績が良かった
・事故の発生件数が少なく、自殺や暴力犯罪も少なかった
との結果を示している研究が紹介してあり、植物がヒトの心身に及ぼす影響に関する興味が一気に湧きあがっていたのでした。
そこで、この現象についてもっと深掘りできそうな本はあるかな〜と探してみたところ、今回紹介する『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』に出会ったわけです。
こうして自分が今読むべき本が数珠繋ぎのように連鎖していくのってめっちゃ楽しいよね!大量の読書をしてきた人なら伝わるはずだ!
そもそも森林浴って何?
で、本を手に取ってみたはいいものの、読み進める前に「そもそも森林浴って何なんだろう?」という疑問が湧いてきたので、スマホでラクしてインスタントな答えを手に入れる前に、まずは少し頭を回転させて考えてみました。
そこで僕の頭に浮かんできた森林浴のイメージは……
・ただ森の中でのんびりリラックスしながら過ごすこと。
・あるいは、森の中を歩き回って意識的に森の空気や匂いを楽しむこと。
・もしくは、森林浴のための特別なプログラムをこなさないといけないのかな?
みたいな感じ。
リラックス・リフレッシュするために森林の中で過ごすのはどれにも共通しているけど、具体的にどんな行為をとれば森林浴と言えるのかがよく分からんな…。
そう思いながら本のページをめくってみると、イントロダクションにこう書いてありました。
森林浴とは、簡単に言うと、ゆっくりと森の中を歩くことです。
『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』*1
(途中略)
すべての感覚を使って自然と触れ合い、森林環境を浴びるのです。
なるほどな〜と頷きながら、今度は国語辞典を開くとこう書いてありました。
しんりんよく【森林浴】
旺文社 国語辞典 第十一版
森林を散策し、樹木の香気を浴びたり清浄な空気を吸ったりして、精神的なやすらぎを得ること。
とまあ、森林浴とはこんな感じらしいです。
これらに加えてネットで色んなサイトを巡回しながら考えたところ、僕の森林浴に対する解釈は、心身に良い影響を与えることを目的として森林の環境と触れ合いながら散策することに落ち着きました。
ま、大きく外してはいないでしょう!

この本のここが面白い!
森林浴という言葉の意味について考えてみたところで、お次は内容の紹介です。
個人的に興味深かった内容とそれに対する感想を、テーマごとにまとめてみますね。
ヒトの体は自然環境用に作られている
この本で最も強調されていると言っても過言ではないのが、ヒトの体は自然環境用に作られているということ。
Back-to-nature theory(自然回帰理論)とのタイトルが付けられたページに、これを象徴している文章があったので引用してみます。
人間は、人間となって約700万年が経過しました。仮に産業革命以降に都市化、人工化したと仮定した場合、その期間は2〜300年間に過ぎず、人間は99.99%以上を自然環境下で過ごしてきたことになります。
『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』*1
(途中略)
遺伝子は数百年という短期間では変化できないため、私たちは自然環境に適応した体を持って現代社会を生きているのです。必然的に、常にストレス状態にあります。
これを読んで僕は、この文章こそが、この本が最も伝えたいコアの部分ではないかと思いました。
ヒトの体は自然環境用に作られているけど、都市化が進み日常生活が自然環境と切り離されてしまった今、ヒトは本来居るべき環境に居ないよね。だからストレスにまみれるのは当然だよね。みたいな。
我流で別の言い回しをしてみると……
ヒトは本来の生息地である森林に適応しながら進化してきた。しかし、急速な高次意識の発達に伴う急速な生息環境の都市化に心身の進化が付いていけていない。従って、自然環境用の体で都市化された環境に常に身を置いている状況は、アドレナリン全開で常に警戒が必要な人類未踏の場所に身を置いている状況と大差はない。そのような交感神経優位の状況(血圧・心拍数↑ / 呼吸・消化↓)が日常生活として長期間続けば、慢性的なストレスによる何かしらの症状が出てくるのはさも当然であると。
そして、都市化された生活によるストレスを軽減させ、心身共にバランスの取れた状態を取り戻すには、森林浴をはじめとする自然セラピーによって自然との繋がりを保ち続けることが大切なんだよ。
こんなメッセージこそが、この本が優しく訴えかけてくれている最も大切な内容であると感じました。
「ヒトにとって本当に幸せな生活って何だろう?」という疑問については、ありとあらゆる人間によって、ありとあらゆる議論がこれまでに繰り広げられてきたと思います。僕自身、その疑問に対する答えは、ヒトの根源的で本質的な部分にヒントが隠されていると感じていて。それは例えば、観葉植物や畑に植えた作物の成長をウキウキで眺める自分に農耕民族のDNAを感じることだったり。YouTubeに動画を載せてる自然農をやってる埼玉の兄ちゃんが「やっぱね〜、畑に出るとね〜、ハイになりますよね〜」って言ってることだったり。過酷な登山中にどこからか水の流れる音が聞こえてきたらホッと安心することだったり。
キレッキレの五感でこのような感覚を寄せ集め、生活の拠点が都会だろうが田舎だろうがそんなことは関係なく、集めた感覚を工夫して生活に落とし込んでいくことで、本当の幸せについて何か見えてくるものがあるんじゃないかな〜と考えたりするわけです。
こんなことを思っている今日この頃、この本が訴えかけているヒトの体は自然環境用に作られているという紛れもない事実は、僕の心の中にスーッと馴染んだのでした。

自然セラピーはヒトの心身にどう影響するのか?
お次は、森林浴のような自然セラピーがヒトの心身に与える影響について。
この本の著者は宮崎良文さんという、千葉大学の名誉教授の方。紛れもない森林浴研究の第一人者であり、森林浴に関する論文を数多く執筆されています。そのためこの本にも研究によってしっかりと裏付けられたデータが多く示されており、この本を読み込めば、「やっぱり自然は癒されるな〜」というなんとなくの感覚が「なるほどそういう仕組みか!」という確かな感覚に変わってきます。
例えば、森林浴研究の歴史を紹介している部分では、下のように記されています。
森林浴の生理的効果に関する実験は、1990年3月に屋久島において私が初めて実施しました。ちょうど、実験開始時に測定指標として確立された唾液中のコルチゾール(ストレスホルモン)を指標として、NHK(日本放送協会)の協力のものと、行いました。その後、10年間ほど、生理的データの蓄積は、進まない状況が続きましたが、2000年に入ってからは、脳活動や自律神経活動計測法の進歩や計測機器の開発が急速に進み、ここ15年ほどで、急速にデータ蓄積がなされつつあります。
『Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー』*1
このように、森林浴をはじめとする自然セラピーがヒトの心身に与える影響を調べる際は
・ストレスホルモンの濃度(唾液中のコルチゾール濃度)
・脳活動の強度(前頭前野の活動量)
・自律神経活動の強度(副交感神経・交感神経の活動量)
が指標として用いられているようです。
他にも、心拍数、血圧、免疫機能(血液中のナチュラルキラー細胞活性)などといった指標が用いられることもあることが紹介されています。
実際に2005〜2006年に日本の24箇所の森林で、森林浴がヒトに与える影響を調査したものをまとめると、森林環境で歩行や座観を行なった時は、都市環境でそれらを行なった時よりも
・ストレスホルモンの濃度が低下した
・心拍数や血圧が低下した
・交感神経の活動が鎮静化した
・副交感神経の活動が活性化した
との結果が得られており、森林にはリラックス効果があるということが判明しています。*2
このような結果が得られた理由としては、ヒトは500万年以上もの間自然環境下で生活してきたためヒトの身体機能が自然環境に適応しているからではないか、と考察されています。*2
ちょっと小難しい話をしてしまいましたが、このようなメカニズムにより、私たちが森林に囲まれた瞬間に「なんか落ち着くな〜」という感情が湧き起こっているようです。
そしてやはりここでも、ヒトの体は自然環境用に作られているというお話が出てきましたね。ヒトが持つ本来の性質を理解しておくことは、人生をコーディネートしていく上でとってもとっても大切なことのように思いました。

気軽に始められる森林浴以外の自然セラピー
これまでは森林浴がヒトの心身に与える影響について紹介してきましたが、自然の力を借りてリラックスモードに入るためには、森林浴の他にもさまざまな方法があることが紹介されていました。
それは例えば、このようなもの。
・都市にある公園の中を歩くこと
・観葉植物や盆栽を眺めること
・花を眺めたり、香りを嗅いだりすること
・木材に触れたり、香りを嗅いだりすること
これらの方法も森林浴と同様、セラピー後には交感神経活動の鎮静化や副交感神経活動の活性化が見られ、実際にリラックス効果があることが実証されているようです。*1
「森林浴でリラックスしたい!」と思ったはいいものの、特に都会にお住まいの方は森林まで距離があることもしばしば。正直移動にも体力を使います。
しかし、上に挙げたような室中でも実践可能な自然セラピーの効果が実証されている今、それらを楽しく積極的に生活へと取り入れていくことができるんです。
・都会を歩くときも、公園の中を通ってみたり、緑の多い道を探し出してみる。
・近くの園芸店や盆栽屋に行って、佇まいが気に入った植物を連れて帰ってみる。
・色や香りが気に入った花を買って帰って、花瓶に挿して楽しんでみる。
・アロマポットにエッセンシャルオイルを垂らして、植物の香りを楽しんでみる。
などなど、ちょっとした工夫と楽しむ心があれば、たとえ都会に住んでいようが可能性は無限大!

さいごに
最後まで読んでくださりありがとうございました!
個人的には、植物がヒトの心身に与える影響について好奇心が湧いていた中、この本に出会えたのはとてもいい流れでした。おかげで、植物と人間との関係性への解析度が格段にアップした気がします。
この記事で何度も紹介しましたが、ヒトの体は自然環境用。したがって特に都会暮らしでは気付かぬうちにストレスを抱えがちですが、森林浴をはじめとする自然セラピーを意識的に取り入れることで、しっかりとオフモードの時間も確保できるように暮らしを工夫していけたらいいですね。
オフを存分に楽しむことで、より充実したオンの時間を過ごせるようになるんじゃないかとも思ったり。
参考にした情報
*1 宮崎良文, 2018. Shinrin-Yoku(森林浴) 心と体を癒す自然セラピー. 創元社, 大阪, 191pp.
Shinrin-Yoku(森林浴): 心と体を癒す自然セラピー
森林浴はなぜ、心と体を健康にするのか?
私たちは自然環境に適応した体で生きてきた。そのため、現在の人工化された都市社会において、ストレスによる心身の不調が社会的な問題になっている。
本書は、海外でも注目を集める著者の英語による著作を逆輸入。自然由来で低コストであり、ストレス軽減、リラックス効果、予防医学的効果のある森林浴について、科学的研究データに基づいて解説。
森林浴を体験できる場所や具体的なプログラムをはじめ、自宅で手軽に取り入れることができる、フラワーアレンジメントや観葉植物、木材、香りなどの効果も紹介。自然と触れ合うことで、心と体を健康に。
*2 Bum Jin Park, Yuko Tsunetsugu, Tamami Kasetani, Takahide Kagawa, Yoshifumi Miyazaki, 2010. The physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experiments in 24 forests across Japan. Environ Health Prev Med 15: 18-26.